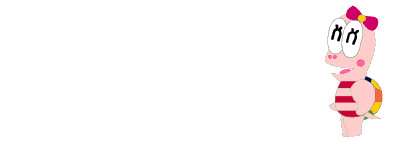| |||
| 「同じ数字に対してジャンプする人はかならず同じです。そのつど違うってことはないから、それは心配しないように。だいたい、わかったかな?」。とくに質問は出ない。みんな、早くやりたそう。「ただし、はじめは5回しかできません。いいですかあ」という説明に、えっ、5回だけなのと声があがる。やみくもに、片っ端から試すことはできない。5回の試行で、なんらかの見通しをたてなくてはならない。ソフトがそう設計されている。 | |||
| |||
| 「[f・6]を押して、自然数を入れて、リターンキーを押してください」と操作方法を確認。このエリア教材を使うために必要な操作説明は、実際、これだけである。まずこれをやって、次にこうして、といった手順は必要ない。 [f・6]に対応する画面のシステムメニューには《問題》と表示されているし、自然数を入れるようにと黄色い記入ボックスにメッセージも出る。とりたてて覚えなくてはならない操作はない。しいてポイントがあるとすれば、リターンキーを押すということぐらい。操作はじつに簡単なのだ。 | |||
| |||
| 授業開始のチャイムからここまでで、所要時間約5分。先生の説明の手際のよさもあるが、「★をつかめ」というソフト自体がわかりやすく、すっきりと作られているからだろう。テンポがいい。 「みなさんのほうに画面を戻します」。そうか、いままで生徒側のコンピュータには先生のコンピュータ(親機)の画面が送信されていたらしい。これも、ちょっとしたコツにちがいない。なにせ、たいがいの子どもはものおじしないでコンピュータを触る。それ自体は好ましいことだが、説明や確認をするためには、しばし「おあずけ状態」にしておくほうが無難というものだろう。 | |||
| |||
 いよいよ、みんなが取り組み始める。 いよいよ、みんなが取り組み始める。[f・6]を押して提示される問題はきまっている。全員、同じ。 「先生、数字を消すにはどうしたらいいの?」と質問が出る。その程度で、とくに操作が問題になっている様子はない。「操作で困っている人はいない?」と先生。しかし、救援を求める声は出ない。 話し合う声や笑い声が響く。みんな楽しそうで意欲的だ。2分ほど経過した頃、はや、「先生、終了になったらどうしたらいい?」と声がかかる。「終了になったら終わり」と先生。 |