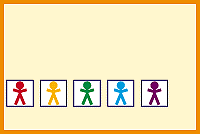| ||
| 「今日は“星をつかめ”という授業をやりたいと思います」という玉置先生の第一声で授業が始まる。 いや、実際は、「お願いします」の挨拶や、生徒からかかった「緊張しとる」の声に「緊張感が伝わってる? 言うなよ、プレッシャーがかかるから」という応酬や軽いやりとりがあった。自然にクラスが和んだところで冒頭の一言。生徒たちには、どういう単元の学習かは知らされていない。 では、玉置先生の説明を聞いてみよう。 | ||
| ||
ここでホワイトボードに貼った黒塗り楕円のUFOの絵に、隕石だ、ブラックホールだとあれこれ評価が飛び出す。とてもシンプルなUFOである。 「そして、『自然数を入れてください』というメッセージが出る」 ここで「自然数って何だった?」という質問に、「正の整数」と答える生徒、別の生徒が「0は入らない」と言う。 「何か自然数を入れると、ある『きまり』にしたがって人がジャンプする。数字によって、1人ジャンプをしたり、2人ジャンプをしたり、5人ジャンプをさせることができるようになっています。 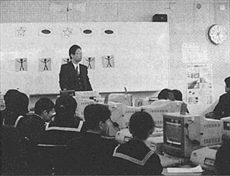 うまく星のところまでジャンプすると、星をつかんだということでマルが出る。 うまく星のところまでジャンプすると、星をつかんだということでマルが出る。UFOのところへジャンプしてしまうと、やっつけられてペケが出る。今日は、どういうふうに星が降ってきたときに、どんな数を入れたら、確実に星の下の人だけをジャンプさせることができるかということを見つけてほしい」 | ||
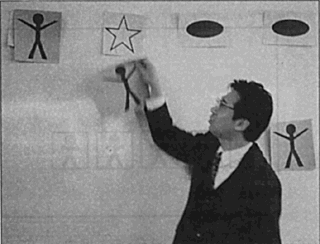 | ||
| ||
| 教室がざわざわっとする。「UFOのところに行くと人は死ぬってこと?」と誰かが言い出す。別のところから「復活する!」と声があがる。「[f・6]を押すと復活します」と玉置先生。笑い声が起きる。 この「★をつかめ」は、ゲーム仕立てになっているが、ゲームの構造はとくに凝ったものではない。いたってシンプルである。 |