| |
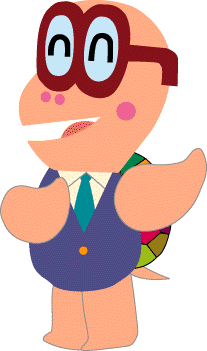 前頁の、2. 授業記録作成の原則と留意点でのべたことは、原則的にはコンピュータを導入した授業でもそれ以外の授業でも共通に当てはまることである。では、コンピュータを使用した授業の記録の場合、特に重要な留意点は何だろうか。これが小西氏から今回与えられたメインの宿題でもある。その宿題への私の答案は次の通りである。 前頁の、2. 授業記録作成の原則と留意点でのべたことは、原則的にはコンピュータを導入した授業でもそれ以外の授業でも共通に当てはまることである。では、コンピュータを使用した授業の記録の場合、特に重要な留意点は何だろうか。これが小西氏から今回与えられたメインの宿題でもある。その宿題への私の答案は次の通りである。まず、何といってもコンピュータを使った授業の記録で一番大切なのは、子どもが操作する対象となるコンピュータのディスプレイ画面そのもののしくみに関する情報である。私は当初、それらの情報も授業記録本体の中に織り込めるのではないかと考えていた。しかし、実際にやろうとしてみると、その方針では授業記録があまりに長々と中断される結果となり、不適当なものであることがわかった。 そこで、今回の記録では<A.自作エリアのメイン画面>というパートを授業そのものの記録とは独立させて紹介することにした。エリア・ソフト「当たるのはどこ?」の説明は思い切って平易に書かれている。これは重要なポイントである。私のような素人から見ると、自作ソフトの機能の説明はたいていが隔靴掻痒でわかりにくい。書き手がそのことについて知りすぎているからである。私は中学生が読んで理解できるというぐらいを目標にして<A>のパートを書くようにしたらよいと思う。子どもの目線で、そのプログラムをロードしたコンピュータの前に座るとはたしてどんなことがおこるか、ということを説明するような感覚で書きたい。 そうすれば、そのソフトを用いた授業のしかけのポイントが何であるか、<A>の記述だけでもかなり想像できるようになるはずである。次に<B.指導案>では授業者が用意したものをそのまま転載する。このパートもはじめ私はある程度詳しい授業記録があえば不要であると考えていた。しかし、指導案は授業の流れを概観するには大変有利なものであることも確かである。指導案だけでは授業の実際は分からないが、指導案なしでは教師の側の授業の構想の骨格を知る上で不便である。 以上のことから原則としてコンピュータを使った授業の記録は次の3部構成に落ち着くのではないかと考えた。 | |
| |
| これだけ揃えばほぼ完璧である。授業は形式をかえて三度語られることになる。3種類の異なる情報が補い合う形となっている。 しかし、・・・と、ここで私は不安になる。本号の特集はfind outのエリア・ソフトの開発者である全国の先生方に、それら自作ソフトのありがたみを授業の事実をそえて他のユーザーにアピールすることを勇気づける(エンカレッジする)目的で企画された。ところが私が書いてきたことはそれとは反対に、むしろ多くの先生を滅入らせる(ディスカレッジする)ものになっているのではないか、という不安である。「やれやれ、そんな大変なことならとても手を出せない」ということになっていないだろうか。これでは逆効果である。  私が提出したのは、ほんの一つのサンプルにすぎない。find out上に開発された、またはこれから開発され続けるであろうエリア・ソフトは、プログラムの規模においても内容においても実に多様なものになるに違いない。<A、B、C>の3つのカテゴリーはどのソフトにも等しく必要なものとは考えられない。ソフトの種類によっては、簡単なソフトなら<A>の説明が十分行われるだけで<B><C>は不要になるというケースもあるにちがいない。その情報だけで読者は授業の構想が頭に浮かべることができるということもありうる。また、<A>と<B>だけで、十分授業の概略が思い描けるという場合もあろう。 また、<C>の授業記録本体も、この授業記録ほどの長さを必要とするとは限らない。もっとも短くても授業のイメージが伝わることも多いだろう。 たいていの場合、授業の記録者は授業者と重なっているであろうから、ビデオはもちろんのこと写真を撮るのもむずかしいことが多いだろう。また、記録の文体は三人称ではなく一人称となるだろう。それには有利な点もあるが不利な点もある。ともかく制約された条件の中でいかにして授業の事実を有効に伝えるかが問題である。 私の今までの経験では、教育界では一つの定式が提案されるとあまりに律儀にそれに従ってしまい、定式にしばられて別の可能性を考えられなくなるということが多いように思う。本稿でストップモーション方式による授業記録法という一つの定式を提案した私がそれを言うのは矛盾しているようだが、ようはfind outのエリア・ソフトを使った授業のよさを文字記号でうまく他者に伝えるというのが最終の目標である。そのために役立つならば、この提案の一部分だけをつまみ食い的に利用することも一向にかまわないというのが私の立場である。おおいにつまみ食いしていただきたい。 できあいの形式の枠にとらわれず、「気軽に自由に授業を書きとめ、交流しよう」というのが私の最大のメッセージであることを感じとっていただければ幸いである。 | |
| |
Benesse Corporation find out通信第19号より転載 |